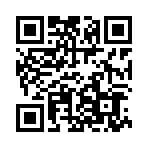2016年03月08日
山神社(山ノ神神社)・その弐、木花佐久夜比命編。
 前日記の続き。
前日記の続き。この山神社(山ノ神神社)は、山の女神で安産の神。
(火伏せや酒造の神威が有るとされるが…詳しくは後述。)
行った当日は、たまたま暦では『丙・戌』の日だった為に、
(前々日記のひなまつり、十進法と十二進法の話の処。十干・十二支。)
安産・子安の祈祷が多く、午前中は駐車場に入り切らないぐらい参拝者が多かったそうな。
(我輩が行ったのは午後からだが、それでも参拝者は途切れず、駐車場も塞がってた。)
さて、その主祭神だが…
咲夜さーん(←違w…そりゃ東方だ。)
もとい、『木花佐久夜比賣命』。
…はて??実に違和感が有る。
(確かに安産の神には間違い無かろうが…)
東北地方では良く『山神』と彫られた石碑は目にするが、
『木花佐久夜比賣命』と彫られた石碑は、我輩の知る限りは無い。
(リサーチ出来てるのは、ほんの一部故に何処かに有るかも分からんが…)
『山神』とは元々、縄文時代・先住民からの『自然神・豊饒神』で女性神だ。
…つまり、元々の先住民の『山神』が後から来た大和人によって『木花佐久夜比賣命』に『同定された』と考えて良かろう。
最初の小山田氏の、個人家系の氏神として祀られた時から木花佐久夜比賣命だったのだろうか??
…いや、社伝によれば1571年に小牛田の町割りの際、御神体を奉じて1575年に祠を建てたと有るので、
おそらくこの時から木花佐久夜比賣命が祀られた可能性が高い。
…火伏せや酒造の御利益が有るとされたのも、この頃からだろう。
それ以前は、特定の名を持たぬ『山神』としての信仰対象だったからこその『山神社(山ノ神神社)』だろうし、
おそらく、それ以降も別に『木花佐久夜比賣命』という神名は、参拝者にとってどうでも良い事だったろう。
(あくまで日本神話という『お伽噺』の神として。)
この山神社の境内には『山神永代獸〜』(←下は埋もれて判読不能)の石碑も祀られてる。
…これは『獸』の文字から判断するに、動物の慰霊碑であろう。元々の山神・豊饒神に対する感謝でも有る。
近くに『牛飼』の地名も有る事から、農作業に使役された牛の慰霊碑かも知れない。
(馬頭観音の牛バージョン?)
この石碑は、寛永年間の建立である事から、その年代に於ても東北地方では日本神話や木花佐久夜比賣命というのは、余り民衆には理解されて無かったのかも知れない。
面白い事に、仙台市南西部の秋保神社にも、この山神社から勧請された石碑が有る。
続きを読む
Posted by 黒猫伯爵 at
11:27
│Comments(0)
2016年03月08日
山神社(山ノ神神社)・その壱、北極星編。
 土曜日に思い立って山ノ神神社に行って来た。
土曜日に思い立って山ノ神神社に行って来た。…ちょうど小牛田駅で東北本線・山側線廃線跡の写真展が有ったので、そのついでと行ってはアレだが。(苦笑)
前々から気にはなってた神社だし、確かめたい事も有ったので。
地元では『山ノ神(やまのかみ)』で通じる程メジャーな神社では有るが、
実は余り行った事が無かった。(苦笑)
山の上では無く、平地の真ん中に有りながら、何故『山ノ神』なのか??
山ノ神という位だから、山岳信仰・北極星信仰が基の神社に違いない。
…それを確かめに、今回思い立って行った訳だ。。
正式には『山神社(やまのかみしゃ)』。
まず参道、鳥居の前で方位磁石を取り出し確かめる。
…間違いなく拝殿・本殿に続く参道は、真北に向かって伸びており、
参拝者も拝殿・本殿正面、真北に向かって参拝する形だ。
周辺の道路・土地区画から考えても偶然に真北になったのでは無い。
狙って真北の方角を意識している。
北極星信仰を意識した造りになってると見て間違いない。
しかも社殿の作りは、外観からの判断だが、所謂『権現造り』に近い様だ。
(日光東照宮のタイプ。修験道系。)
…但し、現社殿は昭和初期の遷座造営なので、最初から北極星信仰の要素を持つ神社だったかは疑いの余地は残す。
(逆に、昭和初期の段階に於てさえ、北極星信仰の残滓が有った事が驚きでも有るが。)
実は宮城県内には、墓地に隣接して同様の遺構が今でも残ってる場所が複数有る。
…随分前にも書いたが、墓地の隣にストーンサークル跡とおぼしき円形の場所が有り、必ずその円形の北側に社・祠が建てられてて『〇〇霊場』と掲げられてたりする。
今から僅か30年程前までは、その円形の場所の中心に柩を置き、参列者が柩の周囲を左回りに3周する葬儀の風習が当たり前に見られたものだが…
(この風習は東北地方が中心で、西日本には無いそうだ。)
休題閑話。
続きを読む
Posted by 黒猫伯爵 at
08:31
│Comments(0)
2016年03月05日
世事想論。
 気付けば卒業シーズン&大学生の就職活動シーズンか。
気付けば卒業シーズン&大学生の就職活動シーズンか。昨日も、就活生とおぼしきスーツ姿の若者がスマホ片手にヤ●ト・ホーム・コ●ビニエンス(←※ク●ネコヤ●トの会社名。)までの道順を訊ねて来たが…
あそこは 止 め と け ! …と思わず言いそうになった。(苦笑)
…つーか、スマホのナビでも分からんかったんかい!!!(笑)
方向音痴は女性に多いと聞くが、その例に漏れないな。
まー、今の学生さんは大変ねぇ…
(否、我々の頃も大変だったが、その内容が全然違う。)
んで何故か、このアーティストの曲を思い出して、
久々にCD引っ張り出して聞いてる。
(…そー言えば今やSDカードやメモリースティックが主流で。お店にCDプレーヤー持ち込んだら前世紀の遺物扱いされたわwww←)
知らずに選んでた
前へと進むレールがずっと遠くまで続いてる
ごめんね これからは
僕は汚れてしまうよ
何にも知らないふりして
この濁った空を飛んでゆくよ
(『明日』の歌詞より抜粋)
…まー、今の時期にピッタリな歌詞やね。(苦笑)
汚れた大人に染まるんじゃないよ、若人逹よ。(←おぃw)
遠くに描き続けた自分を壊す事だって出来たけれど
この手に触れてしまった今では
もう何もかも遅すぎる
君と夢は同じくらい 僕にはとても大切だけど
ここから ふたつに別れる道の 両方は歩けない
(『君と夢』の歌詞より抜粋)
…こーゆー人生の大選択を迫られる若人逹も多いのだろうな。
はて、我輩が卒業・就職した頃は、どうだったろう?
我輩が小さな子供の頃(1980年前後)なんて、
路線バスが走ってる道路ですら砂利道の未舗装区間が多く残ってたからね。
で、就職先なんざ無くて。
役場か・農協か・百姓やるか…くらいしか選択肢が無かった。
(あとは『出稼ぎ』に行くしか無かった。)
…昭和の高度成長だのバブル景気だのなんざ、どこ吹く風。
映画『三丁目の夕日』のレベルにすら追い付いて無くて、あの映画の世界は何処の国のお話??…という感覚しかない。
これが地方の実態だった。
…否、現代の日本に於てすら、この様な僻地が有る。
そりゃ職を求める若人が都会に出て、田舎は人口減少・大都市一極集中になるわな。
で、終身雇用前提の教育で、手に職を…という事で、就職率の高かった工業学校に行ったは良いが…
卒業してみたら世の中は既に就職氷河期で終身雇用なんか既に無かったし、
世の中のコンピューター化が進んでて、工業学校で習った技術が最早時代遅れで、まるで役に立たなかったという…(苦笑)
我輩が通った当時は工業学校でもパソコンの授業なぞ皆無だったが、
我輩の2〜3コ下の連中は普通にパソコン使った授業有ったってゆーからね。
…こんな世の中になるなんて、当時は予想も出来なかった。
我輩の同級生で大学に行った奴は、クラスで5〜6人。
当時の大学進学率なんて、そんなモンで。
…今の様に、半数以上が大学・専門学校に進学して、
企業側も求人の応募条件に大卒以上なんてのは少なかったが…
(むしろ大学に行く奴より自衛隊に行く奴の方が多かった。
兵隊というのも、喰い扶持として数少ない選択肢だった。)
我々の世代が、特に貧乏クジ引かされた世代とも言えるが…
自分の努力が及ぶ範囲では無かったしな。
これだけ世の中の変化スピードが速くなると、
学生時代に将来を見据えて進路選択をする…なんてのは、事実上無理な話で、綺麗事だと思う。
今の学生さん・就活生は我々の世代よりも、恵まれてるなぁ…、と思う一方で。
やっぱり世の中の変化スピードが速過ぎ、又、将来も見通せないという意味では、
大変だなぁ…とも思った一件で御座いました。
Posted by 黒猫伯爵 at
09:14
│Comments(0)
2016年03月02日
本当は恐い、ひなまつり。(悪魔の四方山話。)
たまには悪魔らしい話をしようか。
…つーか、ここ数年、恒例になってるなー。
桃の節句に、このシリーズの話をするのは。(苦笑)
これまで『雛祭り』というのは古来は流し雛という厄祓いで、
それが平安時代の貴族が娘を天皇(お内裏様)と政略結婚させたい呪詛に変わった事、
そして去年は3月3日…数秘学で『3』は『聖数』と述べた。
この3月3日・『桃の節句』だが。
そもそも『節句』は5月5日の『端午の節句』、9月9日の『重陽の節句』などと並ぶ節目のひとつ。
端午の節句は兜を飾り、成人の立身出世を願い、
重陽の節句は菊香酒で長寿を祈願する。
この『節句』という概念は『十進法』という数学的な部分で割り当てられたと考えられる。
陰陽思想では、1年(季節)も1日(時間)も人間(人生、生老病死)も同じく『十二進法』で割り当てるが…
人間の人生・生老病死のタイムスケジュールを『十進法』の暦、『節句』でも当て嵌めたと考えられる。
古代の暦の『還暦』に習い、60歳を基準に仮定し、1年と人生双方を十進法で十分割して解釈してみよう。
その場合、まず1年の始まり、1月1日・元日が人生では0歳の『誕生』に該当する。
そうすると、3月3日・桃の節句は11〜12歳頃。
…女の子が初潮を迎える頃である。
そら、女の子の祭りになるわな。(笑)
そして5月5日・端午の節句は20〜22歳頃、
まぁ成人式を過ぎた頃だが青年の年代に当て嵌まる。
立志式、或いは元服の年代かも知れない。
7月7日の七夕は…36〜40歳頃か。結婚して家庭を持つ頃。
七夕は彦星と織姫というのも頷ける。
(この点は、むしろ結婚限界期だったかも知れない。苦笑)
そして9月9日・重陽の節句は、長寿を祈願する日。
人生で言えば残り僅か、中年から老境の頃。
そら切実に長寿を願いたくもなる。(苦笑)
…どうです?人生・生老病死の進み方と面白い程一致して頷けるでしょ?
そして10月10日は60歳に該当し、
1年を十進法で考えると『ゼロ』の位ですね。
そこから次の桁に位が上がって翌年。
新年1月1日、再生・誕生に戻る。
人間の赤ん坊は10ヶ月と10日の間、母親の腹の中に居ると言われるが、
これもまた偶然だろうか??
…人間は死んで再び生まれ変わるという、陰陽の輪廻転生思想で言えば、『死と再生』なのだろう。と考えると。
平安時代に既に『十進法』の概念は有り、
古代人は『十二進法』と『十進法』の両方を組み合わせて使っており、
かなり数学的な能力も高かったと考えられる。
この『十進法』の概念が、いつごろ何処で発生し、いつごろ中国に伝わり陰陽思想に組み込まれて暦・節句になったか。
(旧暦も十二支と十干の組み合わせだ。)
…これは歴史や考古学的にも非常に興味深い点だ。
この極めて精緻な数学的概念を『易学』も持っている。
…『易』は『統計学』と謂われる所以だ。
ごく単純に、この上記の例で言うと…
初潮が人生で桃の節句に当たる年頃・平均値よりも早く来れば、
その人の人生タイムスケジュール自体も早まっている=即ち『短命』という理屈づけには、なる。
…あくまで単純な喩え話なので、実際の易学はもっと数学的に複雑精緻なんだけどね。(苦笑) 続きを読む
…つーか、ここ数年、恒例になってるなー。
桃の節句に、このシリーズの話をするのは。(苦笑)
これまで『雛祭り』というのは古来は流し雛という厄祓いで、
それが平安時代の貴族が娘を天皇(お内裏様)と政略結婚させたい呪詛に変わった事、
そして去年は3月3日…数秘学で『3』は『聖数』と述べた。
この3月3日・『桃の節句』だが。
そもそも『節句』は5月5日の『端午の節句』、9月9日の『重陽の節句』などと並ぶ節目のひとつ。
端午の節句は兜を飾り、成人の立身出世を願い、
重陽の節句は菊香酒で長寿を祈願する。
この『節句』という概念は『十進法』という数学的な部分で割り当てられたと考えられる。
陰陽思想では、1年(季節)も1日(時間)も人間(人生、生老病死)も同じく『十二進法』で割り当てるが…
人間の人生・生老病死のタイムスケジュールを『十進法』の暦、『節句』でも当て嵌めたと考えられる。
古代の暦の『還暦』に習い、60歳を基準に仮定し、1年と人生双方を十進法で十分割して解釈してみよう。
その場合、まず1年の始まり、1月1日・元日が人生では0歳の『誕生』に該当する。
そうすると、3月3日・桃の節句は11〜12歳頃。
…女の子が初潮を迎える頃である。
そら、女の子の祭りになるわな。(笑)
そして5月5日・端午の節句は20〜22歳頃、
まぁ成人式を過ぎた頃だが青年の年代に当て嵌まる。
立志式、或いは元服の年代かも知れない。
7月7日の七夕は…36〜40歳頃か。結婚して家庭を持つ頃。
七夕は彦星と織姫というのも頷ける。
(この点は、むしろ結婚限界期だったかも知れない。苦笑)
そして9月9日・重陽の節句は、長寿を祈願する日。
人生で言えば残り僅か、中年から老境の頃。
そら切実に長寿を願いたくもなる。(苦笑)
…どうです?人生・生老病死の進み方と面白い程一致して頷けるでしょ?
そして10月10日は60歳に該当し、
1年を十進法で考えると『ゼロ』の位ですね。
そこから次の桁に位が上がって翌年。
新年1月1日、再生・誕生に戻る。
人間の赤ん坊は10ヶ月と10日の間、母親の腹の中に居ると言われるが、
これもまた偶然だろうか??
…人間は死んで再び生まれ変わるという、陰陽の輪廻転生思想で言えば、『死と再生』なのだろう。と考えると。
平安時代に既に『十進法』の概念は有り、
古代人は『十二進法』と『十進法』の両方を組み合わせて使っており、
かなり数学的な能力も高かったと考えられる。
この『十進法』の概念が、いつごろ何処で発生し、いつごろ中国に伝わり陰陽思想に組み込まれて暦・節句になったか。
(旧暦も十二支と十干の組み合わせだ。)
…これは歴史や考古学的にも非常に興味深い点だ。
この極めて精緻な数学的概念を『易学』も持っている。
…『易』は『統計学』と謂われる所以だ。
ごく単純に、この上記の例で言うと…
初潮が人生で桃の節句に当たる年頃・平均値よりも早く来れば、
その人の人生タイムスケジュール自体も早まっている=即ち『短命』という理屈づけには、なる。
…あくまで単純な喩え話なので、実際の易学はもっと数学的に複雑精緻なんだけどね。(苦笑) 続きを読む
Posted by 黒猫伯爵 at
03:40
│Comments(0)